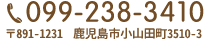2月主題 和合(なかよくします)
仏さまの教えによって、結ばれやわらぎ親しみ合うことや、教えに集う人々が仲良くすることを「和合」といいます。一般の社会においても、仲良くしている人々の和を乱すのは慎むべきであることは言うまでもありませんが、仏教では教えに集う人々の和を故意に乱すような悪しき行いは、大変な罪悪であるとして厳しく戒められています。
日頃、子ども達は園でのお参りの時に、仏さまに「おやくそく」をしています。その中の一つに『わたくしたちは みんな なかよくいたします』という言葉があります。それを、ただ単に口にするだけに終わることなく、実際に行動に反映して行けるような保育を心がけて行きたいものです。
そのためには、日常の園生活の中で、友達と一緒に楽しく遊ぶことを通して仲間意識を持たせるような配慮をしたり、トラブルが生じた場合には、相手やみんなの立場にたってものを考える機会を与えることを大切にするようにしたいと思います。またその一方、集団においては、自己中心的な振る舞いが、いかに他の人に迷惑をかけるかということに気付かせると共に、それが転じてやがて他の人を思いやる心へと発展して行くように導いて行きたいものです。
園生活の中でしばしばおこる子どもの「けんか」は、あえて奨励すべきものではありませんが、けれども一概に否定すべきものでもないと思います。なぜなら、まだ自己の欲求を自身で上手くコントロールすることが難しい子ども達が、お互いの欲求をぶつけ合って、「けんか」という形でそれを解決しようとすることは至極当然のことだからです。そして、そのような体験を経て、次第にそれぞれの年齢に応じた解決策を、自分自身の頭で考え発見して行くようになるからです。
このような意味で、「けんか」は自分を律する力を身につけて行く上での大切な一過程であり、他者との人間関係を学ぶことの出来るまたとない良い機会だともいえます。思えば、私達は日頃、常に「自分は正しくて、相手は間違っている」という前提に立ってものを言い行動をしていますが、争いを通してその解決策を模索する中で、相手の立場になって考えることにより、いつも自分だけが正しい訳ではないことに気付いたり、相手を思いやったり出来るようになるものです。
したがって、もし「けんか」の場面に遭遇した時には、けんかが起こった発端や内容はさておき、子ども自身は双方共に「自分は正しい」という立場で争っているのですから、決してどちらか一方を悪者にして他方に謝らせるのではなく、常に助言者という形で関わり、「どうすれば、お互い仲良く出来るのか」ということについて、子ども達と一緒に考えて行くようにしたいと思います。
年長組
〇相手の気持ちになって考え、仲良く助け合うことの大切さを知る。
〇友達の話を聞いたり、自分の考えを話したりして伝え合う喜びを味わい、友達とのつながりを深める。
年中組
〇仏さまについての話を通して、思いやりの気持ちを持ち、だれとでも仲良く遊ぶ。
〇相手の気持ちを考えながら遊ぶ。
〇身近なものを生かして自分なりに工夫して遊ぶ楽しさを味わう。
年少組
〇仏さまの話を通して、人の役に立つ喜びを知る。
〇誰とでも仲良く遊ぶことの大切さを知る。
〇食事のマナーを守り、食事の大切さを知る。
満3歳児
〇生活や遊びの中で、自分の思いを言葉で伝えたり、相手の気持ちに寄り添ったりしながら遊ぶ。